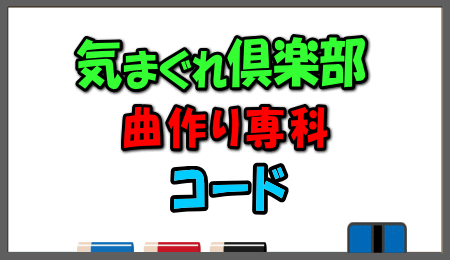
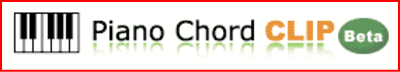
�L�[�ʂ̑���̃R�[�h���A�]��`�����Ō����T�C�g

������Ƃ������̊m�F�ɕ֗��ȃE�F�u�s�A�m
�� �R�[�h���w�ԑO��
�R�[�h���w�Ԃ��߂ɁA�������̎��O�m�����K�v�ł�
�܂��ŏ��ɑ�\�I�ȉ������m�F���Ă����܂��傤
�� �C�^���A�ꁁDo Re Mi Fa Sol La Si Do�i�h �� �~ �t�@ �\ �� �V �h�j
�� ���{�ꁁ�n �j �z �w �g �C �� �n
�� �p�ꁁ�b�c�d�e�f�`�a�b
�� �h�C�c�ꁁ�b�c�d�e�f�`�g�b�i�c�F�[ �f�[ �G�[ �G�t �Q�[ �A�[ �n�[ �c�F�[�j
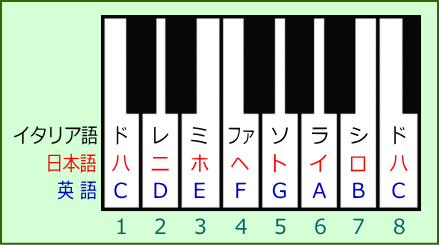
���̒��ō���g�p����̂́u�p��75���v�u�C�^���A��20���v�u���{��5���v���x�ł��傤��
����͉p��\�L�������ƃR�[�h�̗������������������˂Ă��邩��ł�
��F�u�b�Ƃ��������v�́u�h�v�������Ɠ����Ɂu�b�Ƃ����R�[�h�v�́u�h�~�\�̘a���v�������܂�
�܂����{��ł̓n�����A�C�Z���ȂǂƌĂ�ł���u���v���p��ŕ\�L���܂�
��F�n�������b�A�C�Z�����`m�i�������ʓI�ɃL�[�Ə̂��܂��j
�]�k
�Ȃ��h�C�c��͐̂̃v���y�t�ł͓�����O�Ɏg���Ă��܂��������݂͉p�ꂪ�قƂ�ǂł�
���݂̌|�\�E�̈ꕔ�ł��̖̂��c�͂����ċ��K�Ȃǂł̎g�������Ɠ��ŗL���ł�
��P�F�Q���T��~���c���f��i�f�[�}���Q�[�Z���j
�@�@�@�@
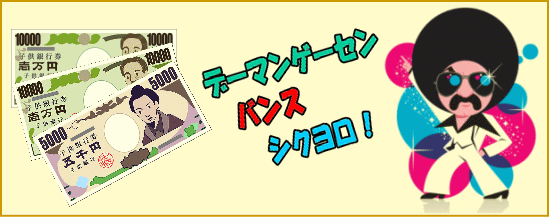
��Q�F�P���V��U�S�~���b���g��`�S�i�c�F�[�}���n�[�Z���A�[�q���N�j
�@�@�i�b���`�F�[�Ɣ�������l�������ł��j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
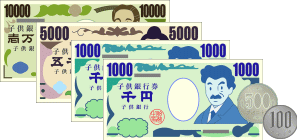
���Ȃ݂ɂW��~���I�N�^�[�u�Z���A�X��~���i�C���Z���ł�
���Ղ̉��̐����́u�b�����[�g�̂P�x�v�������ꍇ�̂��ꂼ��̉����̓x���ł�
�܂��ŏ��Ɋo���Ă������́u�h���b���P�x�v�u�\���f���T�x�v�Ȃ�
�C�^���A��Ɖp��̉����\�L�Ƃ��̓x���ł�
���̐����̓R�[�h���w�ԏ�ŏd�v�ȈӖ������������܂��̂ł�������Ɗo���Ă����܂��傤
�R�[�h�̓A���t�@�x�b�g�Ɛ����̑g�ݍ��킹��u�{�|�^�v���̋L���ŕ\�L���܂�
�ʏ��ʓI�Ɏg����R�[�h�͂P�I�N�^�[�u�ȓ��ŁA�R���������͂S���̘a���ō\������Ă��܂�
�P�I�N�^�[�u���z���������܂ރR�[�h�́u9�x�v�u11�x�v�u13�x�v������
�u�e���V�����R�[�h�v�ƌĂт܂��i��q���܂��j
��{���̊�{����������Ă����܂����M�^�[�t�҂��܂��͌��Ղō\�����w��ł�������
���Ղ̕��������ڂł����_�I�ɂ��o���₷���Ǝv���܂�
�� �����i�C���^�[�o���j
�R�[�h�̐����̑O�Ɂu�����v�ɂ��ĊȒP�ɂӂ�Ă����܂�
��ʓI�Ɏg���Ă���u�����v�Ƃ́H
�̂̉���Ȑl�Ɂu���̐l���������ˁI�v�Ƃ����悤�Ɏg���܂����
����͂����قړ�����O�̂悤�Ɏg���Ă��܂��Ă�̂�
�Ԉ���Ă��Ă������Ă��炢�܂��傤��
���́u�����v�Ƃ͂����������̂ł͂Ȃ��Q�̉��̍����́u�ւ�����v�̂��ƂȂ̂ł�
�u�����͓x���v�ŕ\���܂�
�L�[���b�̏ꍇ�i�b���W���[�E�n�����j
��{�ƂȂ鉹�́u�b�i�h�j�v�ł��̉������[�g�i�����j�ƌ����܂�
�R�[�h�ɕt�����Ă��鐔���̓��[�g���琔�����x���Ȃ̂ł�
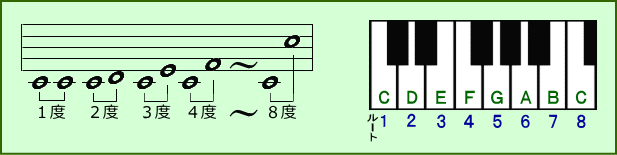
�u�b�Ƃb�i�h�ƃh�j�v�̉����͂P�x�ł�
�u�b�Ƃc�i�h�ƃ��j�v�̉����͂Q�x�ł�
�u�b�Ƃd�i�h�ƃ~�j�v�̉����͂R�x�ł�
�@�@�@�@
�u�b�ƂP�I�N�^�[�u��̂b�v�̉����͂W�x�ł�
���̉����̓x���͖������Ŋo���Ă�������
������́u���[�g���b�v�̗l�X�ȃR�[�h��������Ă����܂�
�� ��{�R�[�h�i135�x�j
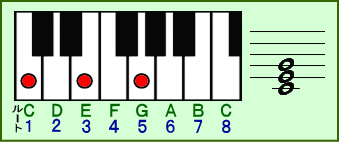
�R�[�h�u�b�v�͉����u�b�d�f�v�̂R���ō\������Ă��܂��i�ɁF�h�~�\�j
�����x���ŕ\���Ɓu�P�E�R�E�T�x�v�ɂȂ�܂�
����āu�b�v�Ƃ����R�[�h�͗��_��u�b�P�R�T�v�ƌĂԂ̂������ł�
����������ł͒�������̂ŏȂ���Ƃ���͍폜���܂��傤
�܂��u�P�x�v�ł�������̓��[�g�����R�[�h�����˂Ă���̂Ŗ������ŏ����܂���
���Ƃ́u�R�x�ƂT�x�v�ł����Ƃ肠�����Q�Ƃ������Ă݂܂��傤
�ł��\����������������Ȃ̂œ��̒��ł́u�P�E�R�E�T�x�v��Y��Ȃ��ł�������
�����Łu�b�v�Ƃ����R�[�h�̓��W���[�R�[�h�Ƃ������Ƃ��m�F���Ă����܂���
���W���[�R�[�h�̑��Α��݂Ƀ}�C�i�[�R�[�h������̂ł��̏ꍇ�u�b�v���u�b���v�ɂȂ�܂�
���W���[�ƃ}�C�i�[�̈Ⴂ�́u�R�x�v�̉��������Ⴄ���Ƃł�
�b���W���[�́u�R�x�v�́u���R�x�v�ʼn��ł����Ɓu�d�v�ł�
�b�}�C�i�[�́u�R�x�v�́u�Z�R�x�v�ʼn��ł����Ɣ������������u�d��v�ł�
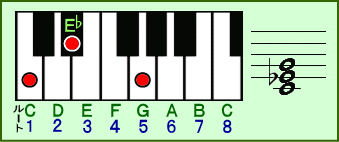
�u�b�v�ƁuCm�v�̈Ⴂ�͂R�x�̉��̈Ⴂ�݂̂ł�
�u�b�v�̒��R�x�̉��u�d�v�������A�Z�R�x�́u�d��v�ɂ����̂��uCm�v�ł�
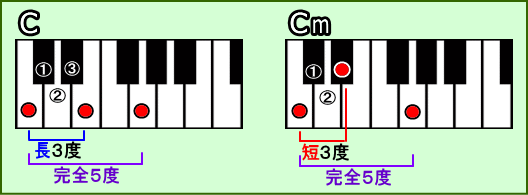
�u�T�x�v�̓��W���[���}�C�i�[���ω��Ȃ��u�f�v�̂܂܂Ȃ̂ŕ\���͏Ȃ��܂�
���̏ꍇ�̂T�x�́u���S�T�x�v�i�p�[�t�F�N�g�t�B�t�X�j�ƌ����܂�
����āu�b���W���[�v�́u�P�E�R�E�T�x�v�̑S�Ă��Ȃ��āu�b�v�ƕ\����
�u�b�}�C�i�[�v�́u�P�E��R�E�T�x�v�́u�Z�R�x�v���u���v�ƕ\�����uCm�v�ƂȂ�܂�
���ׂẴR�[�h�̒��Łum�v�ƕ\��������̂́u�Z�R�x�v�����ł�
�����Łu�R�[�h�v�ł͂Ȃ��u�L�[�v�Ƃ��Ă̕\���̊m�F�����Ă����܂�
�u�L�[�����v�Łu�L�[�b�v�̏ꍇ�́u�n�����v�u�L�[�bm�v�́u�n�Z���v�ƌ����܂�
�p��ł́u�b���W���[�iCmajor�j�v�u�b�}�C�i�[�iCminor�j�v�ƌ����܂�
�`���ŐG��܂������ēx�m�F���܂�
�u�b�Ƃ������v�́u�h�v�Ƃ����P���i���F�n�j
�u�b�Ƃ����R�[�h�v�́u�h�~�\�v�Ƃ����a���i�p�F�b�d�f�j�i�x���F�P�R�T�x�j
�u�b�Ƃ����L�[�v�́u�b���W���[�Ƃ����L�[�v�i���F�n�����j
�P�Ɂu�b�v�Ƃ����Ă��l�X�ȈӖ��������Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��炦�܂�����
�u�b�v�u�b���v�悤�ɂR���ō\������Ă���a�����u�g���C�A�h�R�[�h�v�ƌĂт܂�
�� ��{�`�{�P���̃R�[�h�i�P�R�T�x�{�Z�j
��{�̂R�a���ɂP���������S�a���̃R�[�h�̐��������܂�
��{�͂R��ނ����Ȃ̂ŊȒP�Ɋo������Ǝv���܂�
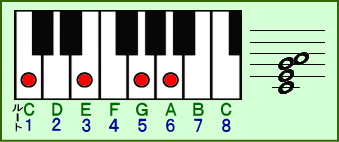
���[�g�́u�b�v���琔���ĂU�Ԗڂ̉��́u�`�v�ł�
�u�b�v�̃R�[�h�Ɂu�`�v���������̂��u�b6�v�ł��i�ɁF�h�~�\���j
���́u�`�v�͊��S�T�x�́u�f�n����P����̉��Ń��[�g�́u�b�n���猩��Ɓu���U�x�v�ɂȂ�܂�
�R�[�h�Ƃ��Ắu�U�v�͂��́u���U�x�v�����Ŕ�����������グ���肷��R�[�h�͕ʂ̖��̂ɂȂ�܂�
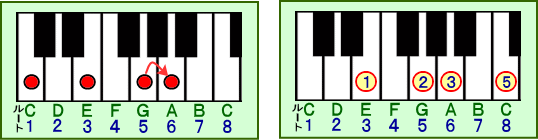 �@�@
�@�@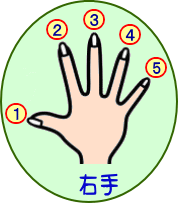
�T�x�̉��̂P���E�ׂƍl����Ɨǂ��ł���
���]��`���e���₷���Ǝv���܂�
���{�̋ƊE�ł͍Ō�́u�X�v�͏Ȃ��āu�V�[�Z�u���v�ƌ����l�������Ǝv���܂�
�Ȍ�u�V�v�̂��R�[�h�ł͕\�����u�Z�u���v�œ��ꂵ�܂�
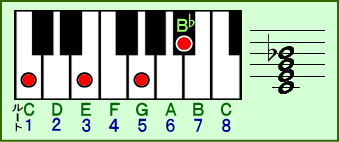
���[�g�́u�b�v���琔���āu�Z�V�x�v�́u�a��v�������܂�
�u�Z�R�x�v�̏ꍇ�́um�v�\�������܂������Z�u���X�R�[�h�͋t�Łu�Z�V�x�v�ł͉����\���͂���
�u���V�x�v�̎��Ƀ��W���[�\�������܂�
���́u�b��7�v�i�V�[���W���[�Z�u���j���Q�Ƃ�������
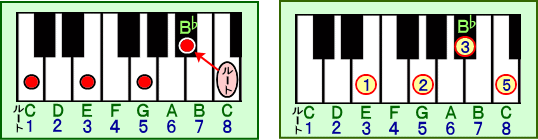
�P�I�N�^�[�u��̃��[�g����P��������������������C���[�W�ł��傤��
���̃R�[�h�����]��`���e���₷���Ǝv���܂�
 �i�V�[���W���[�Z�u���j
�i�V�[���W���[�Z�u���j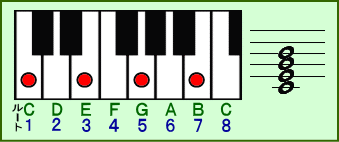
���[�g�́u�b�v���琔���āu���V�x�v�́u�a�v�������܂�
�\���̓��W���[�ł��邱�Ƃ��������āu���E�l�Emaj�v�Ȃǂ�t�����܂�
�ǂ���g���Ă����Ȃ��`���܂��������ł͋L�����g�p���܂�
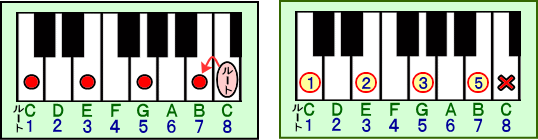
���̃R�[�h�͓]��Ɓu���V�x�̂a�v�����[�g�́u�b�v�Ɨׂ荇�킹�ɂȂ��Ă��܂��܂�
�����W�̉����ɖ炷�ƕs���a����������̂ł��̏ꍇ�̓]��͏o���܂���
�@ �s�A�m�\���̏ꍇ�ō���Ń��[�g���̂b��e�����ꍇ
�A �o���h���t�Ńx�[�X�����[�g���̂b��e�����ꍇ
���̏ꍇ�͉E��͂b���Ȃ��Ă���肠��܂���
���[�g���̂b���Ȃ����ꍇ�̎c��̘a���́u�d�f�a�v�i�ɁF�~�\�V�j�ŃR�[�h�́u�d���v�ł�
����͑㗝�R�[�h�Ƃ��ĕʂ̋@��ɐ������܂�
��L�R��ނ̃��W���[�R�[�h�̒��R�x�̉��u�d�v��������
�Z�R�x�́u�d��v�ɂ���ƃ}�C�i�[�R�[�h�ɂȂ�܂�
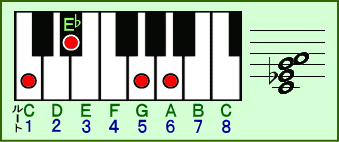
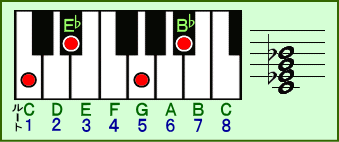
 �i�V�[�}�C�i�[���W���[�Z�u���j
�i�V�[�}�C�i�[���W���[�Z�u���j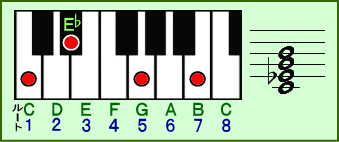
�S�a���̂܂Ƃ�
��{�̂R�a���R�[�h�b�i�P�E�R�E�T�x�j�ɂP�������ďo����R�[�h
�u�R�[�h�b�v�{�u���U�x�̂`�v�@���u�b6�v
�u�R�[�h�b�v�{�u�Z�V�x�̂a��v���u�b7�v
�u�R�[�h�b�v�{�u���V�x�̂a�v�@���u�b��7�v
�����Ă��ꂼ��̃��W���[�R�[�h�̂R�x���������}�C�i�[�R�[�h
�u�bm6�v�u�bm7�v�u�bm��7�v
�R���ō\������Ă���a�����u�g���C�A�h�R�[�h�v�ƑO�q���܂�����
�S���ō\�������a�����u�e�g���b�h�R�[�h�v�ƌ����܂�
�� ��{�`�������ω��������R�[�h
��{�R�[�h�u�b�v�u�b���v�́u�R�x�y�тT�x�v��ω��������R�[�h��������܂�
���̕\���F
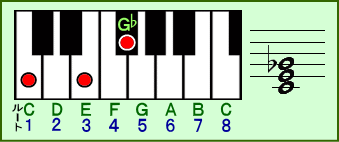
�T�x�̂f�����������R�[�h�ł�
�����Ŕ������グ�����������ɕ\��������@���L���Ă����܂�
���[�g���猩�āu���S�T�x�v�̉����グ��Ɓu���T�x�v�ɂȂ�܂�
�t�ɔ���������Ɓu���T�x�v�ɂȂ�܂�
���{��ł́u�����v�̖��O�͊o����K�v�͂���܂���
�y����ł́u�{�|�v�������́u����v�ŕ\�L���܂��������ł́u�{�|�v�ŕ\�����܂�
�������グ���������R�[�h�ł͌��̉��ƈꏏ�ɒe���ƕs���a���������邽��
���R���̉��͏ȗ����܂�
���̏Ȃ��s�ׂ��u�I�~�b�g�v�ƌ����܂�
���́u�b-5�v�̏ꍇ�͊��S�T�x�́u�f�v���I�~�b�g���邱�ƂɂȂ�܂�
�Ȃ��u�{�|�v�̋L�����g���x���͂P�I�N�^�[�u�ȓ��ł́u�T�x�v�����ł�
�P�I�N�^�[�u�����e���V�����R�[�h�ł�
�I���^�[�h�e���V������ �u�|9�E+9�E+11�E�|13�x�v������܂��i��q���܂��j
���Ȃ݂Ƀi�`�������e���V������ �u9�E11�E13�x�v�ł�
 �i�V�[�v���X�t�@�C�u�j
�i�V�[�v���X�t�@�C�u�j���̕\���F
 �i�V�[�V���[�v�t�@�C�u�j
�i�V�[�V���[�v�t�@�C�u�j�@�@�@�@�F
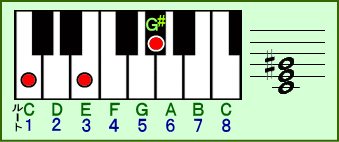
���S�T�x�̂f�����グ���i���T�x�j�R�[�h�ł�
���̃R�[�h�͓���Ȃ̂ŏڂ����������܂�
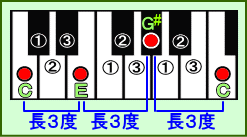
���̃R�[�h�̍\���́u�b�E�d�E�f���v�ł�
���ꂼ��̉��̊Ԃɂ͂R�̉������݂��Ă��ĉ������S�Ē��R�x�ō\������Ă��܂�
�ǂ��������Ƃ��ƌ����Ƃ��̃R�[�h�̓��[�g������Ă��S�ē������F�ɂȂ�킯�ł�
�u�b+5�v�̑��]��`���u�d+5�v�A���]��`���u�f��+5�v�Ȃ̂ł�
�u�f��+5�v�̃R�[�h�͉��ƂȂ�������ł��������������ɂ�
�u�b+5�v���u�d+5�v���p�o����Ƃ������Ƃł�
���̃R�[�h�͕ʖ��u�I�[�M�������g or �I�[�O�����g�v�ƌĂ�Ă���
�u�baug�v�ƕ\������邱�Ƃ������ł��������ł́u+5�v���g���܂�
���Ȃ݂ɂ��̃R�[�h�͗��_�I�ɂS��ނ�������܂���
�e���₷���`�Ŋo���Ă����Ύ��H�ł��Ȃ�y�ɂȂ�܂�
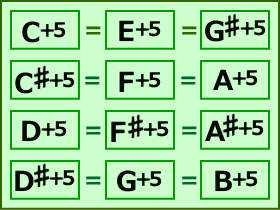
���̕\���F
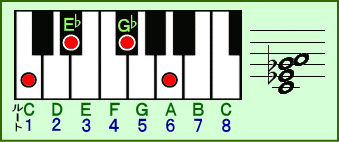
��ʓI�ɂ͗���́u�f�B�~�v�ƌĂ�Ă���R�[�h�ł�
���m�ɂ͂R���́u�b�E�d��E�f��v�Łu�bdim�v
����Ɂu�`�v��������Ɓu�bdim7�v�ƕ\�������̂ł���
�ƊE�̈�ʓI�ȉ��߂Ƃ��Ă͏�L�S���̍\���������āudim�v�Ƃ���̂����ʂł�
�킩��ɂ����̂͂U�x�́u�`�v�������Ă���̂ɂVth�R�[�h�ɂȂ邱�Ƃł�
�܂�����́u�Z�Z�V�x�����V�x�v�Ƃ��ĕЕt�����Ă���̂ł��������[���������܂�����
�����ł͊�����Ĉ�ʓI�Ɏg���Ă���e�g���b�h�R�[�h�Ƃ��Đ������܂�
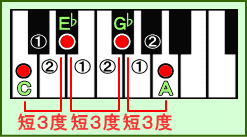
�O�q�́uaug�v�R�[�h�Ƃ͋t�ō\�����̉����͂��ׂāu�Z�R�x�v�Ŋe���Ԃ͂��ׂĂQ���ł�
���ʁu�bdim�v���u�d��dim�v���u�f��dim�v���u�`dim�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂�
�u�f��dim�v���e���Â炢�ꍇ�́u�bdim�v�ł��ǂ��Ƃ������Ƃł�
����Ă��̃R�[�h�͗��_�I�ɂR��ނ�������܂���
�uaug�v���l�e���₷���`�Ŋo���Ă����Ύ��H�ł��Ȃ�y�ɂȂ�܂�
�udim�v���u�Z�v�Ȃ̂ł����ł͊ȒP�ȋL���ŕ\�L���܂�
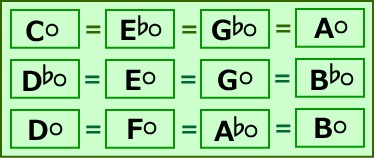
���̕\���F
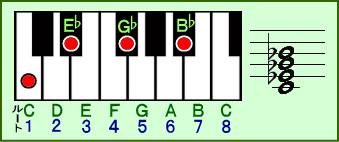
�\�L���Ăі������|�I�ɒZ���u�n�[�t�f�B�~�v���������߂ł�
���̃R�[�h�ɂ͂Q�ʂ�̂Ƃ炦��������܂�
�@�u�b���V�v�́u�T�x�̂f�v�������āu���T�x�̂f��v�ɂ����R�[�h�i�V�[�}�C�i�[�Z�u���}�C�i�X�t�@�C�u�j
�A�u�bdim�v�̂P���i�`���a��j���������オ���Ă���̂Ŕ���dim�i�n�[�tdim�j
���̃R�[�h�͎�Ƀ}�C�i�[�L�[�̎��Ɂu�Wm6�v�̑ւ��Ɂu�U�n�[�t�f�B�~�v���g���܂�
��F�uCm�v�̎��uFm6�v�̑ւ��ɁuD�n�[�tdim�v���g���Ƃ������Ƃł�
�a���̍\���͓����ł������[�g����ς��邾���ŕ��͋C���ς��Ǝv���܂�
�ڂ����́u�R�[�h�i�s�v�̃R�[�i�[�Ő������܂�
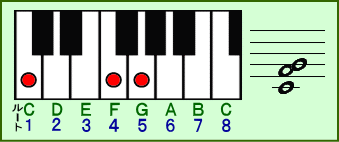
�������́u�T�X�y���f�b�h�t�H�[�v�ł��������̂Łu�T�X�t�H�[�v�Ɨ����܂�
�R�x�́u�d�v���s���a���ɂȂ�̂ŃI�~�b�g���܂����u�d�v����ꂽ���ꍇ��
�e���V�����R�[�h�́u�b(11)�v�Ƃ���Ɨǂ��ł��傤
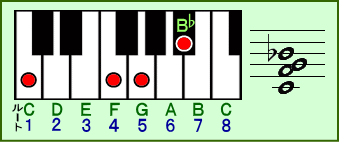
�u�bsus4�v�Ɂu�Z�V�x�v�́u�a��v���������R�[�h�ł�
��ʓI�ɂ́usus4�v��肱�����R�[�h�̕������ʂɎg���܂�
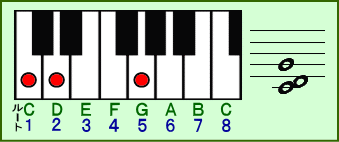
���̃R�[�h�̓N���V�F�I�Ȍ��ʂŌo�߃R�[�h���Ďg���邱�Ƃ������ł�
��F�uCsus4�v���u�b�v���u�bsus2�v���u�b�v
�ƊE�ł͐F�X����p���܂����usus�v���Ȃ��āu�b2�v�u�b4�v�u�b74�v�Ə����Ă��\���ʂ��܂�
�� �X�x�̃R�[�h
���̂ӂ��̃R�[�h�͍��{�I�ɈႤ�̂ł�������m�F���Ă����܂��傤
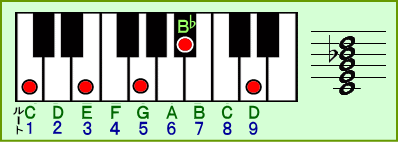
�u�b9�v�͂R�a���{�V�x�{�X�x�Ő��m�ɂ́u�b79�v�ł�
�킩��₷���\������Ɓu�b7�v�{�u�X�x�v�ł�
�Ȃ��u�b��9�v�́u�b��7�v�{�u�X�x�v�ł�
�u�V�x�v����ꂽ���Ȃ��ꍇ�Ɂuadd�v���g���܂�
�u�badd�X�v�́u�b�i�X�j�v�̂悤�Ɂi �j�ŕ��邱�Ƃœ����Ӗ��ɂȂ�܂�

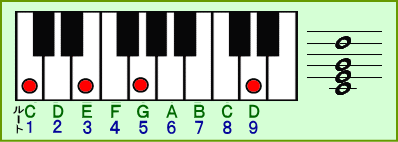
�uadd�v��u�i �j�v��p���邱�ƂŁu�V�x�v�͓���Ȃ��Ȃ�܂�
�u�X�x�v�Ɍ��炸��{�̂R�a���{�P���Ƃ������ƂɂȂ�܂�
��F�u�badd�{11�v���u�b�E�d�E�f�v�{�u�e���v
�@�@�u�b�i�[13�j�v���u�b�E�d�E�f�v�{�u�`��v
�Ȃ��uadd�v�����Ȃ��u�b13�v�Ƃ����R�[�h��
�R�a���ɏ����S���܂܂��̂Łu�R�[�h�b�v�{�u��V�v�{�u�X�v�{�u11�v�{�u13�v�ł�
���Ō����Ɓu�b�E�d�E�f�E�a��E�c�E�e�E�`�v�ƂȂ�܂�
�قڃW���Y�̐��E�Ȃ̂ʼn��̂�̗w�Ȃł́u�X�x�v�܂ŗ}���Ă����Ηǂ��ł��傤
�� �[�X�E�{�X�i��X�E���X�j�̃R�[�h
�u�b�X�v�Ɠ��l�Ɂuadd�v�\�����Ȃ���u�Vth�v�̉�������܂�
�\�����@�ł����u��E���v�ł��ǂ��̂ł����l�I�ɂ́u�|�E�{�v���������߂��܂�
����́u�T�x�v�̎������l�Ȃ̂ł�������킵�����������邽�߂ł�
�Ⴆ�u�a��X�v�̏ꍇ�́u�a��̂X�x�v�Ȃ̂��u�a�́�X�v�Ȃ̂��H
�܂��u�`�����T�v��u�d�X�v�̏ꍇ�͕\���������炢�Ǝv���܂�
���ʂ͎��������ł͂Ȃ����̐l�Ɍ��Ă��炤�̂��߂ɂ��킩��₷������ׂ��ł�
��Ȃ�ҋȂ��d���ɂ��邽�߂ɂ͎ʕ��͍Œ�����ł����y�Ȃ̉���Ȃǂł���o���ɂ�
���ʂ̓Y�t���K�v�ɂȂ�ꍇ������̂œ������猩�₷�������悤�ɐS�����܂��傤
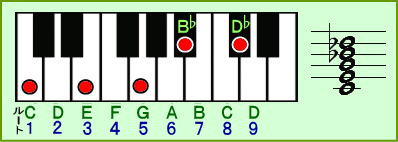
���̃R�[�h�͕��ʏ�Ɏ��ɕ\�����Ȃ��Ă��K�v�ɉ����Ă�����ł��g���ׂ��ł�
�P���ߒP�ʂƂ������o�߉��I�ɒZ�߂ɓ���邱�ƂőS�̂̕��͋C���S�R�ς��܂�
���Ƀ}�C�i�[�L�[�ɂ����Ẵh�~�i���g�R�[�h�̎��ɈЗ͂����܂�
��Ƃ��Ă̓L�[���u�`���v�̎��̃h�~�i���g�V�R�[�h�́u�d�V�v���g����
�o�߉��I�Ɂu�d�[�X�v���u�d�v���u�d�V�v�Ɨ���Ă݂Ă�������
�g�b�v�̉��́u�e���d���c�v�ƂȂ莟�́u�`���v�Ɏ��R�ƂȂ���܂�
 �i�V�[�v���X�i�C���X�j
�i�V�[�v���X�i�C���X�j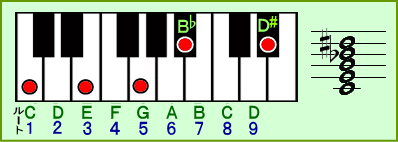
���̃R�[�h����Ƀ}�C�i�[�L�[�ł̃h�~�i���g�Ŏg�����Ƃ������ł��iAm�̎���E+9�j
��ɃW���Y��|�b�v�X�n�Ŏg����R�[�h�ʼn��̌n�̋Ȃł͂قڏo�Ԃ͂���܂���
�ꕔ�̏��a�̗w�Ȃł��g���Ă���̂ŏЉ�Ă����܂�
�� �����R�[�h�i�X���b�V���R�[�h�j�E�I���R�[�h�A
 �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@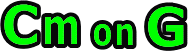
�i�W�[�u���m�V�[�}�C�i�[�j�@�@�@�@�i�V�[�}�C�i�[�I���W�[�j
�����͂��ׂē������t��\�����Ă��܂�
�R�[�h�́uCm�v�Ńx�[�X���u�f�v�Ƃ�������t�ł�\���̃R�[�h�ł�
�s�A�m�\���̏ꍇ�͉E��ŁuCm�v����Œቹ���́u�f�v�̒P����e���܂�
���̎�@�͂��Ȃ�g�p�x�������Ǝv���̂ŕʂ̋@��ɂ�����������������Ǝv���܂�
�����Ƃ��P�Ƃł̎g�p���u�N���V�F�v�ȂǃR�[�h�i�s�̒��ŗ͂����邱�Ƃ������̂�
�������̃p�^�[�����o���Ă����Ƃ��Ȃ���H�Ŗ𗧂��܂�
�� �����܂ł̂܂Ƃ�
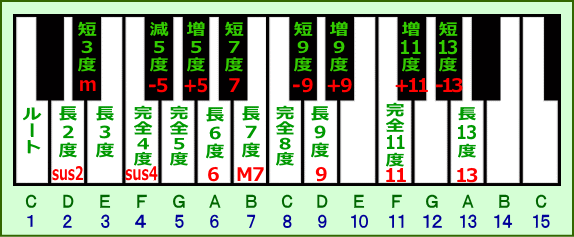
����܂łɏЉ���u�b�R�[�h�v�����Ղɂ܂Ƃ߂܂���
��L�̓��{��̕\���͓��Ɋo���Ȃ��ėǂ��ł�
�u�P�E�R�E�T�x�v�i�ɁF�h�~�\�j����{�Ƃ��ĐԐF�́u�x�v�������܂�
�����ŗאڂ���ꍇ�͌��́u�R�x�v�y�сu�T�x�v�̉����I�~�b�g���܂�
����̓L�[���u�b�v�ɓ��肵�Đ������܂��������̃L�[�ł��l�����͈ꏏ�ł�
�u���[�g�����P�x�v�Ƃ��ĉ��Ԗڂ̉��������邩�Ƃ��������ł�
�悭�g�������ȃL�[�̌��Ր}���ڂ��Ă����܂��̂ŎQ�l�ɂ��Ă�������
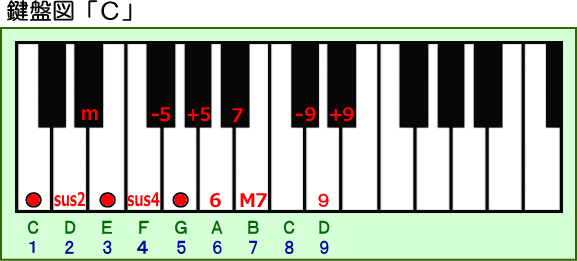
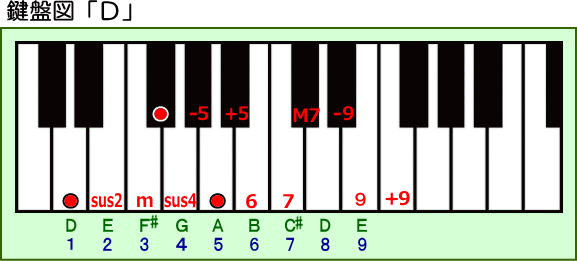
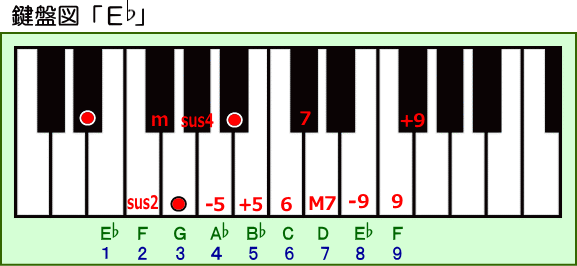
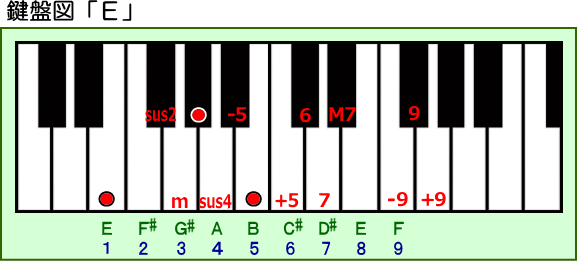
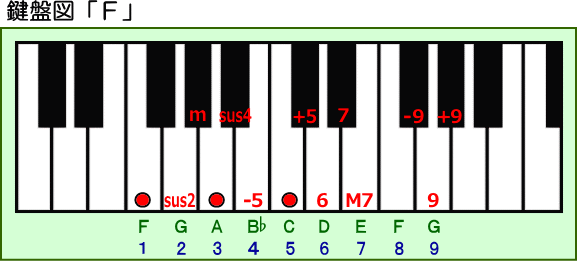
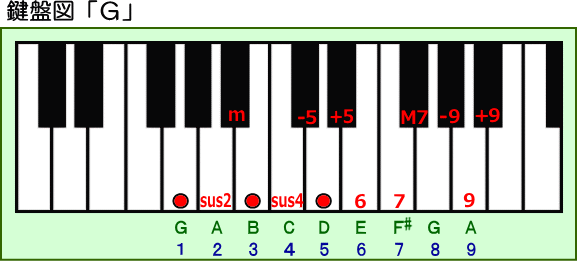
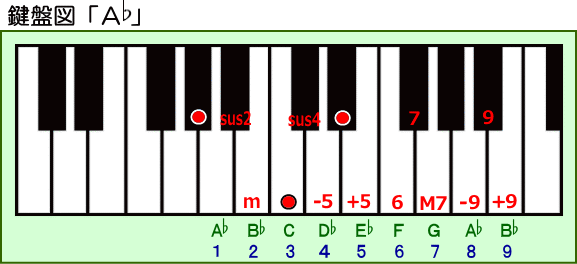
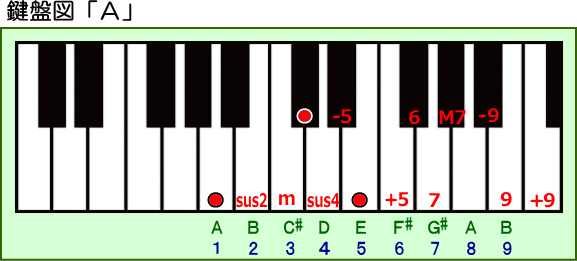
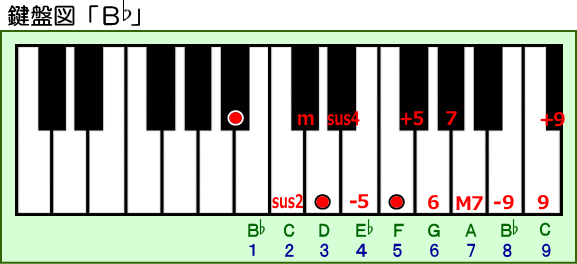
���₢���킹�E����Ȃǂ�����܂����牺�L�t�H�[�����炨�肢���܂�

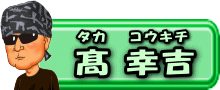
Copyright (C) -2021 takakoukichi.All Rights Reserved