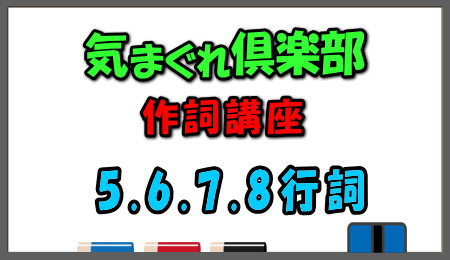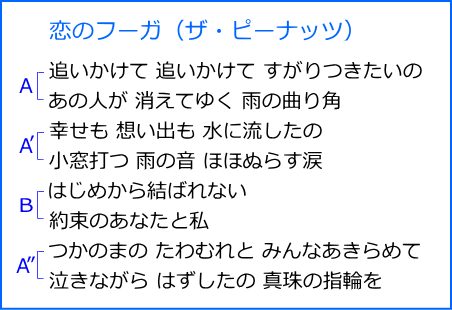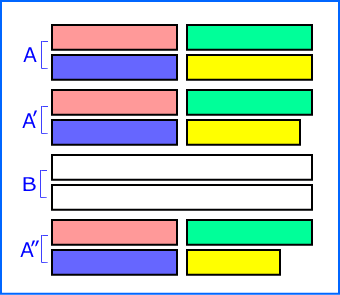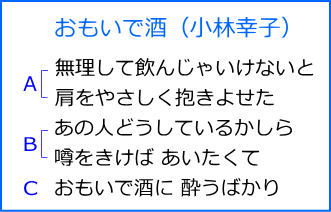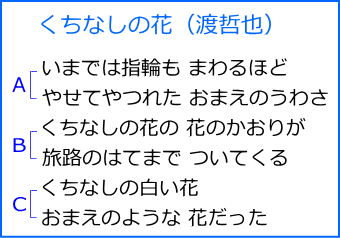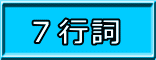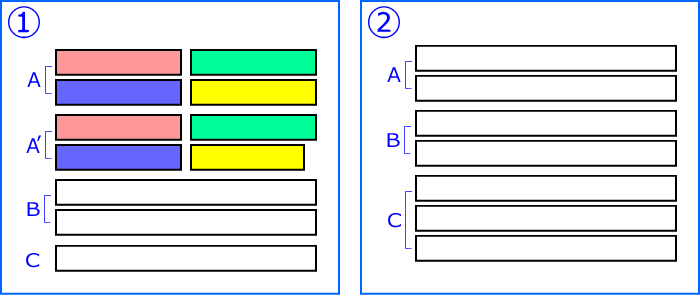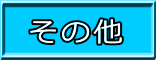作詞の際には「何行」の詞にするかという事から決める場合があります
もっとも作っているうちに1行増えたとか減ったとかはあるとは思います
詞の内容もありますが構成が良くないために作曲家が敬遠する事もあります
ここでは「詞の行」における曲の構成について説明していきます
演歌では「5行詞」と「6行詞」がほとんどです
歌謡曲になると「8行詞」が大半を占めます
「ABC構成」に合わせて順に説明していきます
「8行詞」構成は演歌ではほとんど見られず主に歌謡曲に使われます
ABC構成は「AABA」「AABB」「AABC」のように「AA〜」が多いですが
「ABBC」「ABCC」などのパターンもあります
どのパターンでも同じアルファベットが2つありますが注意点としては
同じアルファベットの行の字脚を揃えるという事です
「AABA」構成の場合は下図の同じ色の部分の字脚を同じにします
なおそれぞれの最後の部分(黄色のバー)は違うメロディを
つける場合が多いので2〜3文字程度の増減は大丈夫です
「AABB」の場合はそれぞれ「A」と「B」部分の字脚を揃えます
「AABC」の場合は「A」部分のみを揃えます
「ABBC」「ABCC」などのパターンでも同じ文字部分を揃えます
「8行詞」もしくはそれ以上の行詞でも「D」が出てくる構成はありません
一般的な歌謡曲は「ABC」の3種類までで構成されます
なので同じアルファベットが必ずあるわけです
これは曲の構成の基本なので「8行詞」を作る場合は気をつけましょう
2行で1パターンですので極力2行ずつ句点がつくように書きましょう
メロディが歪になりますので最悪でも「A’」の最後で一度流れを止めて下さい
全ての行(8行)の最後に句読点を打って流れを確認しましょう
字脚と共に各コーラスで句読点の位置がずれてないかを見て下さい
メロディを付けるにあたってとても重要になります
「AABA」「AABB」の場合は必ず「B」がサビになりますが
「AABC」では「C」がサビというパターンも稀にあります
歌謡曲を8行詞で作る場合は「2ハーフ」が一般的です
2ハーフ = 1番、2番を8行で作成し間奏後サビからの4行で構成します
「5行詞」の構成では「ABC」が多いですが
「AAB」「ABA」「ABB」もないわけではありません
しかし8行詞のように字脚を気にして書く必要はありません
作曲家がどの構成にするかを決めるのが普通です
どの行詞でもそうですが必ず「A」の最後で句点を付けれるように
流れを止めて下さい
作曲上「A」の最後はトニックコード、ルート音を使い
その位置で一度曲の流れを終了させます
「A」から「B」に話が途切れず続いていく構成の詞は
基本的に曲にならないのでコンペなどで落とされる可能性が高いです
前述した各コーラスの句読点の位置ズレも曲になりずらいです
「5行詞」の場合は最後の「C」部分にタイトルを入れる事が多いです
またサビを「C」に持ってくるパターンも多いです
「6行詞」は「5行詞」と同様「ABC」が多いですが
「AAB」「ABA」「ABB」もあります
それらの構成をあえて狙わない限りは「6行詞」の場合でも
字脚に気を使う事なく書いて良いです
演歌の場合は歌謡曲と違いサビを最後に持ってくる事が多いです
その曲のテーマになる部分を「C」に置けば必然的に作曲家が
そこをサビにして作ってくれる事でしょう
「7行詞」は2つのパターンがあります
① 「8行詞」の「C」部分を1行削ったパターン
② 「6行詞」の「C」部分に1行加えたパターン
①は「AABC」 ②は「ABC」となります
どちらも演歌ではなく主に歌謡曲に使われるパターンです
サビは①は「B」 ②は「C」の最後が多いのでその位置に
テーマを入れると良いでしょう
この他には「4行詞」や「8行より多い行数」の詞があります
「4行詞」は演歌というよりも抒情歌などがに多いですね
8行より多い行数では「10行詞」がありますが10行になっても
「ABC」しか使わないので構成が難しいです
最初は「8行詞」で収める事を推奨します
演歌は「5行詞」「6行詞」、歌謡曲は「8行詞」
書いていて増減の必要が出来た場合に「7行詞」
そんな感じでしょうか
今まで構成を考えずに作詞をしてきた方は是非これを踏まえて
作曲家に好まれる詞を書かれると良いでしょう
※ 歌謡曲の正確な定義はありませんがここでは演歌以外の昭和の流行歌を指して説明しています
「歌謡曲wiki」
お問い合わせはこちらから